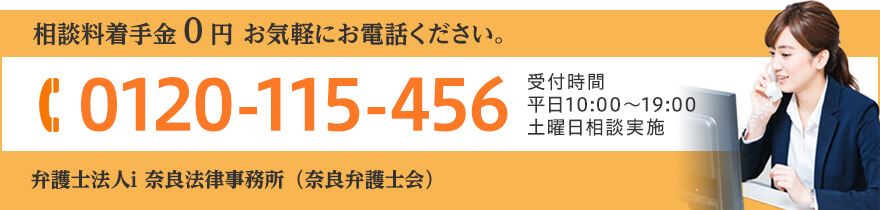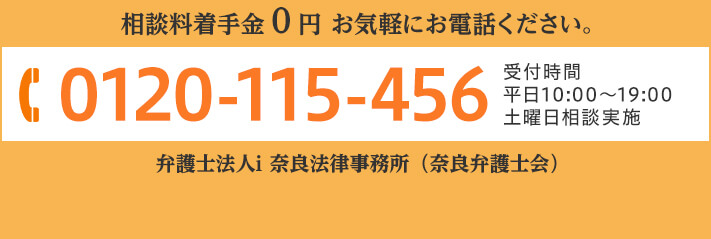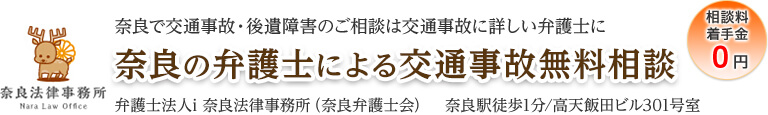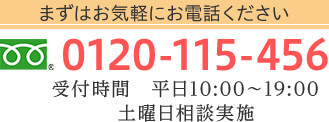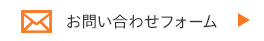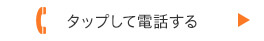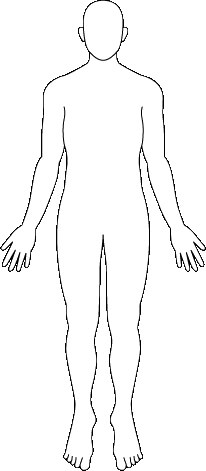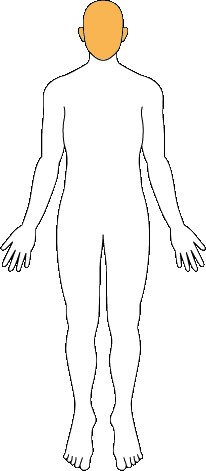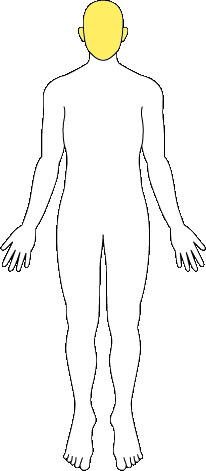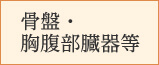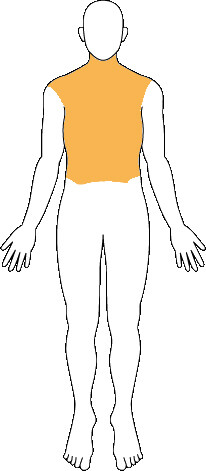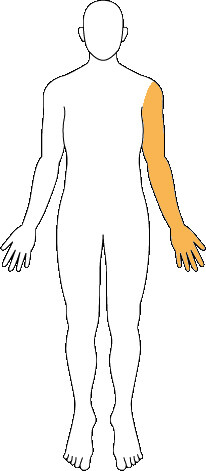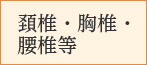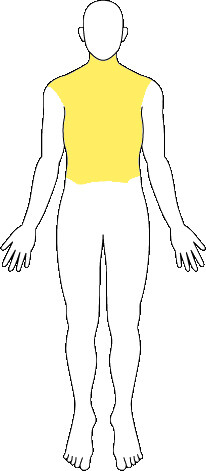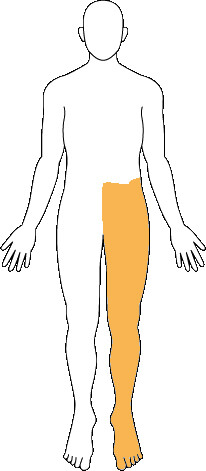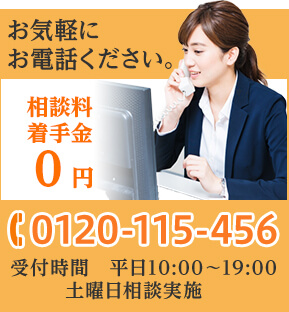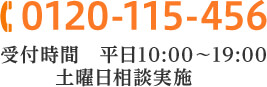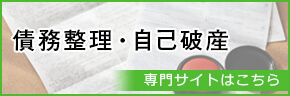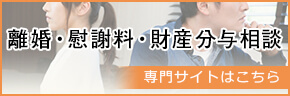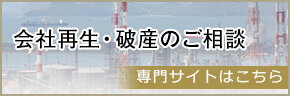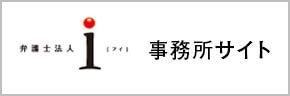耳の後遺障害とは?交通事故で後遺障害が残る場合や等級を解説します
交通事故によって耳に障害が残ると、日常生活に大きな影響が生じます。特に「耳鳴り」「難聴」「耳漏」などの症状は、見た目では分かりにくい一方で、本人にとっては会話が困難になる、音が常時響く、集中できないなど深刻な負担が生じます。このような症状が一定以上のレベルで続き、治療によって改善が見込めない場合には、「後遺障害」として認定される可能性があります。
後遺障害として認められると、損害賠償や慰謝料、逸失利益などの請求が可能になります。反対に、認定を受けられないと適正な賠償額が支払われないことも少なくありません。そのため、耳の症状に不安がある場合は、早い段階で検査や診断を受け、必要に応じて弁護士に相談することが重要です。
耳の後遺障害とは?
交通事故などの外傷によって耳の機能に障害が残り、治療やリハビリを行っても回復が見込めない状態を「耳の後遺障害」といいます。耳は「聴力」「平衡感覚」「外見(耳介)」など複数の機能を担っているため、障害の種類によって認定される等級が異なります。
耳の後遺障害にはどんなものがある?
代表的な耳の後遺障害には次のようなものがあります。
| 症状 | 内容 |
| 聴力障害 | 会話が困難になる・小声や大声が聞き取れないなど |
| 耳鳴り | 常時キーンという音が聞こえる状態 |
| 耳漏 | 耳から分泌液が続く状態 |
| 耳介の欠損 | 事故による耳殻の変形・欠損 |
| 平衡機能障害 | めまいやふらつきなど |
これらは、日常生活の支障だけでなく、仕事や対人関係にも影響しやすいため、症状の程度を正確に把握しておく必要があります。
聴力の後遺障害の認定基準
後遺障害等級は、症状の「程度」と「検査結果」に基づいて判断されます。
特に聴力については、純音聴力検査と語音明瞭度検査が重要な指標となります。
後遺障害の認定基準チェック
耳の後遺障害は「数値で評価できるもの」「自覚症状が中心となるもの」「外傷」 があります。特に「聴力障害」については、検査結果が等級認定のポイントとなるため、どの検査でどの数値がどの程度かを理解しておくとよいでしょう。
認定の判断に用いられる主な指標は次の3つです。
1.平均純音聴力レベル(dB)
どれくらい小さい音が聞こえるかを測定する検査です。
数値が大きいほど「聴こえにくい(難聴の程度が重い)」と評価されます。
2.語音明瞭度(%)
実際の「言葉」をどれだけ聞き分けられるかを測る検査指標です。
会話能力に直結するため、日常生活の困難さや仕事への影響を評価する際に重視されます。
3.距離による音声認知の可否(40cm・1m以上など)
「普通の話声」「大声」「小声」がどの距離で聞き取れるかという実生活に近い評価基準です。
これらの検査結果や症状の持続状況が 「症状固定」 として確認されれば、後遺障害の等級が 4級〜14級の範囲で認定されます。
また、聴力障害のほかに、
・耳鳴り
・耳漏
・欠損
といった症状がある場合は、聴力とは別の基準(12級・14級、または耳介欠損は2級など)が適用されます。
耳は外見上の変化が見えにくい部位であるため「聞こえにくさ」「生活上の支障」などの 具体的な状況を医師に正確に説明することが、認定の大きなポイントになります。
両耳の場合
以下に両耳の後遺障害の認定基準を表にしました。
| 両耳の聴力障害 | 4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの |
| 6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの | |
| 6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの | |
| 7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの | |
| 7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの | |
| 9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの | |
| 9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの | |
| 10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの | |
| 11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの |
一耳(片耳)の場合
以下に一耳(片耳)の後遺障害の認定基準を表にしました。
| 片耳 | 9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの |
| 10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの | |
| 11級5号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの 1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの | |
| 14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの |
その他
耳の後遺障害には聴力を失った場合以外にも以下のような状態で認定されるケースがあります。
| 耳介の欠損 | 2級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 耳介の軟骨部の1/2以上を欠損したもの |
| 耳漏 | 12級 | 常時耳漏があるもの |
| 14級 | その他のもの | |
| 耳鳴り | 12級 | 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの |
| 14級 | 難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの |
参考 後遺障害等級表 国土交通省
聴力の後遺障害の検査方法
交通事故の後に耳が聞こえにくい、音がこもる、耳鳴りが続くといった症状がある場合、まずは聴力の状態を客観的に測定する検査を行います。耳の障害は、外傷がないケースもあるため外見では分からないことが多いのですが、検査をすることで症状を数値化できるため、後遺障害等級の認定において非常に重要な資料となります。
耳の症状は、外見からは分かりにくく、被害者自身が「聞こえにくい」と感じていても、検査数値や診断書の記載が不十分だと、後遺障害として認められないケースもあります。そのため、耳鼻咽喉科など専門性の高い医療機関で、適切な検査を受けることが重要です。
聴力検査
耳の後遺障害では、主に以下の検査が行われます。
・標準純音聴力検査(平均純音聴力レベルをdBで測定する検査)
・語音聴力検査(言葉の聞き分け能力=語音明瞭度を測定する検査)
標準純音聴力検査は「どのくらいの大きさの音なら聞こえるか」を、語音聴力検査は「聞こえた音をどの程度意味として理解できるか」を示します。
同じ「耳が聴こえにくい」という症状でも、生活で感じる困難さや不便さは人によって異なります。これらを医療機関の検査では客観的に数字で評価します。
また、症状が耳鳴りや耳漏を伴う場合には別の検査や聴覚専門医の診断が必要になることもあります。検査結果・診断書・経過記録は、後遺障害認定の重要な証拠となるため、必ず保管しておきましょう。
交通事故で耳の後遺障害が認められることもある
耳の後遺障害は「事故後しばらくしてから耳鳴りが続くようになった」「以前より声が聞き取りづらい」というケースもあります。
外傷がないケースもあるため、本人が気づかないこともありますし、周囲から「気のせい」「ストレスでは」と処理されてしまうこともあります。ですが、症状が続く場合は後遺障害の対象となる可能性があります。
専門医を受診する
耳の障害は耳鼻咽喉科や聴覚検査に対応した医療機関を受診することが大切です。
また、耳の「聞こえにくさ」や「耳鳴り」は言葉で伝えるのが難しい場合があるため、
医師に伝える際は「小声・普通の声・大声」での聞き取りやすさの違いなど、できるだけ具体的に説明できるようにしましょう。
弁護士に相談する
耳の後遺障害の認定は、保険会社と被害者の間で意見が分かれるケースもあります。
保険会社は自社の基準にしたがって判断するため、症状があっても認定が下りないケースもあるのです。
弁護士に依頼して対応することで基準が保険会社の基準ではなく、弁護士の基準になるためより手厚い保障を受けられるということもあります。
・提出書類
・検査記録の整理
・後遺障害等級認定の異議申立て
・適正な損害賠償と慰謝料
・逸失利益の請求
といったステップを踏んで請求するため補償額が大きく変わる可能性があります。
まとめ
耳の後遺障害は、見た目では分かりにくいにもかかわらず、日常生活への影響が大きい障害です。交通事故後に耳鳴り、聴こえにくさ、声が届きにくいなどの症状が続く場合は、早期に専門の医療機関で検査を受け、後遺障害認定を視野に入れて治療と検査、そして、手続きをする必要があります。
聴力検査・語音明瞭度検査・診断書の内容は、等級認定・損害賠償・慰謝料に直結するため正しく診断できる医療機関で検査を受けることが大切です。
保障の内容や手続きに不安がある場合は、早い段階で弁護士に相談することで、将来の生活を守るための補償を適切に得られるでしょう。
この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士
黒田 充宏
開業以来、地元市民の皆様から交通事故に関する多数の相談を受けて参りましたが、残念なのは簡単なアドバイスで解決できることにもかかわらず、ずっと一人で悩んでおられる方が多数いらっしゃるということです。相談後に「誰にも話せずに悩んでいたけれども、もっと早く相談に来ればよかった」と仰る依頼者の方が意外と多いものです。特に交通事故に関するご相談では、「もう少し早く相談してくれれば、適切なアドバイスができたのに」と思うことが多々あります。交通事故の法的トラブルについては、時機を失うと大きな損失につながる可能性があります。「こんなことで相談してもよいのかな」と心配する必要はありません。当事務所では、経験豊富な弁護士がいつでもお待ちしております。身近な町医者として、今後とも精進する所存ですので、困ったときにはいつでもご相談ください。
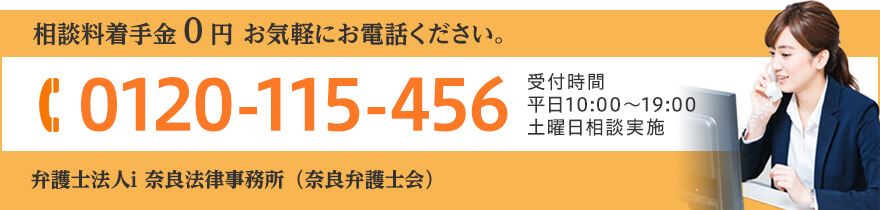
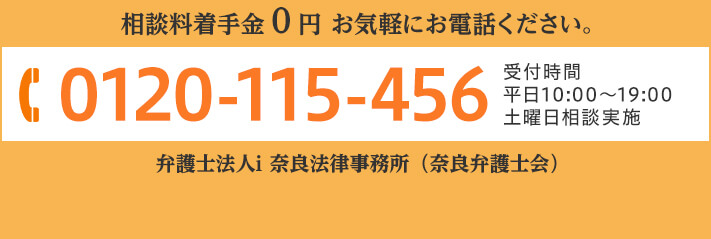
当事務所の解決事例
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。 適正な後遺障害認定を獲得します。
適正な後遺障害認定を獲得します。 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
 事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。
事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。 適正な後遺障害認定を獲得します。
適正な後遺障害認定を獲得します。 費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。
費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。